大阪大学の研究者が語る未来社会
本ページでは、大阪大学の研究者が動画インタビュー・ミニ講義を通じて、自らの研究のルーツ、研究と社会課題の関係性、そして「いのち輝く未来社会」の実現のためにどのような取組を行っているか語っています。
研究者の視点から、多様で複雑に入り組んだ社会課題の解決に向けた糸口をみつけるヒントを提供する内容となっております。是非ご覧ください。
Index
- 近代を超えて~目指すべき社会を考える~【堂目 卓生 社会ソリューションイニシアティブ 特任教授(常勤)】
- プラスチックとの共生 今、プラスチックに何が起きているのか?~プラスチックに突き付けられた課題~【宇山 浩 工学研究科 教授】
- 月経から考えるSDGs【杉田 映理 人間科学研究科 教授】
- エネルギーのサステイナビリティ【下田 吉之 工学研究科 教授】
- 認知症の人のwell-beingをどう考えるか【山川 みやえ 医学系研究科 准教授】
近代を超えて~目指すべき社会を考える~
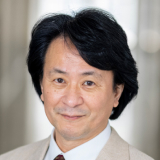
講義概要
18世紀のイギリス経済思想を専門とする堂目先生には、近代社会における科学技術の進歩や経済成長に基づく物質的豊かさの裏側にある、環境破壊や格差の拡大などの多くの課題を克服し、「いのち輝く未来社会」の構築に向けた構想についてお話しいただきました。アダム・スミス、ジョン・スチュアート・ミル、アマルティア・センの3人の思想家による社会構想に加えて、堂目先生の提唱する「助けを必要とするいのち」を中心に据えた共助の理念に基づく社会の実現に向けて何が必要なのか考えるヒントをいただきました。
インタビュー
ミニ講義
プラスチックとの共生 今、プラスチックに何が起きているのか?~プラスチックに突き付けられた課題~

講義概要
バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックの研究を専門とする宇山先生には、プラスチックの歴史を通じてその利点と課題についてお話しいただきました。多種類のプラスチックが混在するためリサイクルが難しいこと、海洋プラスチック問題など環境への影響が深刻であることなど、プラスチックに関する多くの課題に対応するため、環境に配慮した材料開発を進めることの重要性を示していただいています。
インタビュー
ミニ講義
月経から考えるSDGs
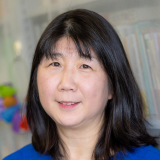
講義概要
文化人類学を基盤とした国際協力学を専門とする杉田先生には、月経がSDGsとどのように関連しているのか解説していただきました。生理現象であると同時に社会的・文化的側面をもつ月経の問題は、教育や貧困、ジェンダー平等など幅広い課題と関わっており、途上国だけでなく先進国でも「生理の貧困」などの問題につながっています。月経をめぐる諸課題に対応するための国際的な月経衛生対処(MHM)の取組について、そして杉田先生のチームを中心に推進されている学内トイレへの生理用品の設置運動などについても紹介いただきました。
インタビュー
ミニ講義
エネルギーのサステイナビリティ

講義概要
エネルギーの問題を専門とする下田先生には、エネルギー需要のモデル化、快適性や健康性といった人々の生活に直結するエネルギー設計など、人口増加と温室効果ガス削減という課題解決のために必要なことについてお話しいただきました。再生可能エネルギーの利用拡大、大気中のCO₂吸収、エネルギー需要削減等を組み合わせたシナリオや、エネルギー消費を抑えるための効率的な技術や行動変容などについて解説いただき、脱炭素社会実現に向けた研究の重要性を示していただきました。
インタビュー
ミニ講義
認知症の人のwell-beingをどう考えるか

講義概要
看護学を専門とする山川先生は、高齢者が活き活きと生活して満足して人生を終えられることを目指して、認知症患者の就労や社会的孤立問題に注目し、医療・企業・地域が連携した支援体制の構築についてお話しいただきました。特に認知症患者のWell-Being(良い状態)について考えられており、患者の個性や生活環境を理解し、適切な支援を行う「パーソンセンタードケア」の体制を構築すること、支援者が患者の時間や感情を尊重し、心地よい環境を整えることが重要であり、そのためには社会全体の協力が不可欠であるとお話しいただきました。
